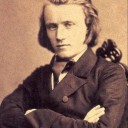今日は大学のセミナーに参加したのだが、そこで面白い話を聞いた。ハエは学習するというのだ。実験はとても簡単で、ハエ100匹を筒の中に閉じ込めてある匂いAを嗅がせる。と同時に電気刺激を与えて痛い目にあわせる。次に匂いBを嗅がせる。この時はなにもしない。そして、半分が匂いA、もう半分が匂いBを発する筒に学習させたハエを移すと、9割以上のハエが匂いBがする方に移るというのだ。
あんなにちっこい奴なのに、しっかり学習のメカニズムを備えている事に驚いた。
あんなにちっこい奴なのに、しっかり学習のメカニズムを備えている事に驚いた。
新しい研究テーマの準備の為に、とあるタンパク質の遺伝子を会社に全合成してもらっているのだが、合成が完了したらしく、あとは日本まで送られてくるのを待つのみとなった。トラッキングナンバーで調べてみたところ、現在はテネシー州メンフィスに保管されているらしい(wikiで調べたらFedExの本拠地とのこと)。番号をでググるだけで宅配物の所在が分かるとは、世の中便利になったもんだと感心しきり。
来週の初めに到着予定とのこと。ワクワクする。
来週の初めに到着予定とのこと。ワクワクする。
クロマトグラフィーの怪
2009年6月3日 学校・勉強今日は実験で逆相クロマトグラフィーを用いてタンパク質の精製をしていたのだが、いつもならカラムを通す事でサンプル中の成分が分離して出てくるはずが、何も出てこないという事態に遭遇した。
せっかくのサンプルが。。orz
サンプルがおかしいのか、装置にロードする際に間違った操作をしていたか、HPLCの装置に何か問題があったか。
とりあえず原因をリストアップし、一つずつ可能性を潰していくしかない。
追伸
後日、先輩が確認したところ誤った使われ方をしている事が判明した。
大いに反省。。
せっかくのサンプルが。。orz
サンプルがおかしいのか、装置にロードする際に間違った操作をしていたか、HPLCの装置に何か問題があったか。
とりあえず原因をリストアップし、一つずつ可能性を潰していくしかない。
追伸
後日、先輩が確認したところ誤った使われ方をしている事が判明した。
大いに反省。。
自分は理系の研究室に所属しているが、ここ一月ほどは全く実験をしていない。というのも、今までやっていたテーマはお蔵入りにして、新しいテーマに移るためだ。そいつで修士論文を書く予定なので、かなり念入りにバックグラウンドを調べる必要がある。
で、ひたすらPCの前に座って論文読み読みとなる。ずーと読んでいると、目が疲れる、姿勢が悪くなる、お菓子や飲み物が欲しくなる。要するに集中力が足りないのだ。(ぉ
かなり時間がかかったが、自分がやろうとしている分野の雰囲気はおおよそ掴めてきた。
来月から本格的に実験に入ることになりそうだ。
で、ひたすらPCの前に座って論文読み読みとなる。ずーと読んでいると、目が疲れる、姿勢が悪くなる、お菓子や飲み物が欲しくなる。要するに集中力が足りないのだ。(ぉ
かなり時間がかかったが、自分がやろうとしている分野の雰囲気はおおよそ掴めてきた。
来月から本格的に実験に入ることになりそうだ。
久しぶりに雨が降る。庭の芝生に水撒きした時の匂いがする。
そういえば久しく田舎に帰っていない。
雨が降るとラジコンができない
やれなくもないがドロだらけになって掃除が面倒だ。
ベアリングが死んだりシャフトが錆びたりするし。
とりあえず、花粉が飛ばないのが一番ありがたい。
そういえば久しく田舎に帰っていない。
雨が降るとラジコンができない
やれなくもないがドロだらけになって掃除が面倒だ。
ベアリングが死んだりシャフトが錆びたりするし。
とりあえず、花粉が飛ばないのが一番ありがたい。
LC-MS/MSが復旧するまでは論文を読む日々になりそうだ。
<今日のまとめ>
RNaseIIIの基質がdsRNAであると最初に報告された論文をざっと読んだ。
・著者はdsRNA,ssRNA,dsDNA,ssDNAの四種類の基質を使って酵素消化実験を行い、dsRNAのみ消化されていた事を確認した。
<次にやること>
RNaseIIIと酵素消化されたRNAの複合体のx線結晶構造解析について書かれた論文を読む。
<ゆくゆくやること>
LC-MSが復旧したら、サンプルを分析し、E3RNaseの基質特異性について調べる。
RNaseLの発現方法の調査、これまでに明らかになっている酵素科学的性質の調査。
<今日のまとめ>
RNaseIIIの基質がdsRNAであると最初に報告された論文をざっと読んだ。
・著者はdsRNA,ssRNA,dsDNA,ssDNAの四種類の基質を使って酵素消化実験を行い、dsRNAのみ消化されていた事を確認した。
<次にやること>
RNaseIIIと酵素消化されたRNAの複合体のx線結晶構造解析について書かれた論文を読む。
<ゆくゆくやること>
LC-MSが復旧したら、サンプルを分析し、E3RNaseの基質特異性について調べる。
RNaseLの発現方法の調査、これまでに明らかになっている酵素科学的性質の調査。
卒研発表前の予聴会が終わった。
とりあえず、発表量を減らす必要がある。
発表の制限時間は5分なのだが自分は7分30秒しゃべっていた。
オーバーしすぎだぉ。。orz
パソコンの設定方法、プロジェクターの使用法等色々と得るところあり。
そろそろスーツを用意しておくか。
本番は来週。
とりあえず、発表量を減らす必要がある。
発表の制限時間は5分なのだが自分は7分30秒しゃべっていた。
オーバーしすぎだぉ。。orz
パソコンの設定方法、プロジェクターの使用法等色々と得るところあり。
そろそろスーツを用意しておくか。
本番は来週。
卒研発表会の要旨集に載せる原稿がようやく完成した。たかがA4一枚なれど、仕上げるのが大変だった。まぁ、おかげで今までやってきたことの整理がついたので得るところ大いにあり、だ。
<今後の活動方針>
・卒研発表用のスライド作り(byパワポ)
・siRNAの酵素消化、切断産物の同定
<やること>
・siRNAの切断により生じえるフラグメントの分子量計算
・in vitroでのcolicinE3の切断実験が書かれた論文の検索・読解
・RNaseL関連の論文の検索・読解
・予聴会の段取り(2回やるか否か、先生の都合、学生の都合、教室の都合)
来年うちに新しく配属される4年生の人数だが、希望者は5人いるようだ。しかも全員男。生物系なのになぁ(w まぁ、猥談で盛り上がるか(ぉ
写真は敬愛するブラームス先生。ひげって人相変えるね。
<今後の活動方針>
・卒研発表用のスライド作り(byパワポ)
・siRNAの酵素消化、切断産物の同定
<やること>
・siRNAの切断により生じえるフラグメントの分子量計算
・in vitroでのcolicinE3の切断実験が書かれた論文の検索・読解
・RNaseL関連の論文の検索・読解
・予聴会の段取り(2回やるか否か、先生の都合、学生の都合、教室の都合)
来年うちに新しく配属される4年生の人数だが、希望者は5人いるようだ。しかも全員男。生物系なのになぁ(w まぁ、猥談で盛り上がるか(ぉ
写真は敬愛するブラームス先生。ひげって人相変えるね。
新しいテーマについてのメモ
扱うもの:RNaseL(2-5A systemで最後に誘導されるリボヌクレアーゼ)
特徴:インターフェロンに応答して産生される。ヒト、マウス、ウサギの細胞で確認(哺乳類に共通の仕組み)。ウイルスRNAの分解、ウイルス増殖の抑制、細胞のアポトーシスに関与。
産生までの流れ:dsRNA or インターフェロンを細胞に投与、2-5A synthetaseとRNaseLの合成誘導→2-5A synthetaseによる2-5Aの合成→2-5AがRNaseLのankyrine loopと結合→RNaseLの構造が変化→RNaseL同士がKinase-like domainで結合し二量体化(RNase活性化)→RNAの分解
リボヌクレアーゼとしての働き:polyUを認識して非特異的に切断。in vitro実験系でU↓U、U↓A、U↓Gでの切断を確認。polyA or C or GやpolydT or A or G or Cでは切断が見られない。
分子量:msのデータはまだ見つけていない。murine RNaseLは65kDA位。(電気泳動後のバンドから判断していた。)
アミノ酸残基数: human:741 murine:679
構造:N末端側からankyrine-repeat domain(23-335)、kinase-like domain(364-583)、nuclease domain(584-720) 特にC末端付近のGlu711からHis720がリボヌクレアーゼ活性に必須の部分となっている。(ちょん切ると活性を示さなくなる。)
発現:murine cell、insect cell、E.coliでの実験系を確認(但し、RNaseLがモノマーの状態でもE.coliに対しては毒性を発揮)
収量:E.coliでの発現では、4Lスケールで1.5mgのrecombinant human RNaseLを得ていた。(E3RNaseでの場合(300mlスケールで10mg)と比べると大分少ない。inhibitorが無いからか。)
<考えておくこと>
・ネズミでやるか、ヒトでやるか。(ネズミ細胞は研究員の人が管理。ヒトの細胞でもいけるのか調べてみる。)
・RT-PCR 経験者がいるようなので、教えてもらう。
・vector 論文ではpKK223-3にクローニングしていた。うちにあるか?無い場合はどうするか?(買うか他のもので代用?)
・E.coli 論文ではJM105 or 109
・発現 growthは相当遅いらしい。final.o.5mMのIPTGで誘導
・精製 イオン交換クロマトグラフィー×2、ゲルろ過クロマトグラフィー、protein liquid chromatography(なぞ) His-Tag精製は使えない?
・切断 活性を高めるには2-5A、ATP、Mg2+ or Mn2+ の添加が必要
追加
酵母のIre1pはRNaseLと相同性あり。ただしこちらはRNAをかなり高い特異性で切断。また、ankyrine-repeat domainは持たず、unfolded protein にsensitiveな部分を持つ。構築するとしたらこちらからの方が楽であろう。論文を読んでみる。酵母菌での役割はmRNAのスプライシングに関与するらしい。
扱うもの:RNaseL(2-5A systemで最後に誘導されるリボヌクレアーゼ)
特徴:インターフェロンに応答して産生される。ヒト、マウス、ウサギの細胞で確認(哺乳類に共通の仕組み)。ウイルスRNAの分解、ウイルス増殖の抑制、細胞のアポトーシスに関与。
産生までの流れ:dsRNA or インターフェロンを細胞に投与、2-5A synthetaseとRNaseLの合成誘導→2-5A synthetaseによる2-5Aの合成→2-5AがRNaseLのankyrine loopと結合→RNaseLの構造が変化→RNaseL同士がKinase-like domainで結合し二量体化(RNase活性化)→RNAの分解
リボヌクレアーゼとしての働き:polyUを認識して非特異的に切断。in vitro実験系でU↓U、U↓A、U↓Gでの切断を確認。polyA or C or GやpolydT or A or G or Cでは切断が見られない。
分子量:msのデータはまだ見つけていない。murine RNaseLは65kDA位。(電気泳動後のバンドから判断していた。)
アミノ酸残基数: human:741 murine:679
構造:N末端側からankyrine-repeat domain(23-335)、kinase-like domain(364-583)、nuclease domain(584-720) 特にC末端付近のGlu711からHis720がリボヌクレアーゼ活性に必須の部分となっている。(ちょん切ると活性を示さなくなる。)
発現:murine cell、insect cell、E.coliでの実験系を確認(但し、RNaseLがモノマーの状態でもE.coliに対しては毒性を発揮)
収量:E.coliでの発現では、4Lスケールで1.5mgのrecombinant human RNaseLを得ていた。(E3RNaseでの場合(300mlスケールで10mg)と比べると大分少ない。inhibitorが無いからか。)
<考えておくこと>
・ネズミでやるか、ヒトでやるか。(ネズミ細胞は研究員の人が管理。ヒトの細胞でもいけるのか調べてみる。)
・RT-PCR 経験者がいるようなので、教えてもらう。
・vector 論文ではpKK223-3にクローニングしていた。うちにあるか?無い場合はどうするか?(買うか他のもので代用?)
・E.coli 論文ではJM105 or 109
・発現 growthは相当遅いらしい。final.o.5mMのIPTGで誘導
・精製 イオン交換クロマトグラフィー×2、ゲルろ過クロマトグラフィー、protein liquid chromatography(なぞ) His-Tag精製は使えない?
・切断 活性を高めるには2-5A、ATP、Mg2+ or Mn2+ の添加が必要
追加
酵母のIre1pはRNaseLと相同性あり。ただしこちらはRNAをかなり高い特異性で切断。また、ankyrine-repeat domainは持たず、unfolded protein にsensitiveな部分を持つ。構築するとしたらこちらからの方が楽であろう。論文を読んでみる。酵母菌での役割はmRNAのスプライシングに関与するらしい。
最近は図書館に潜る事が多い。今扱っているテーマが割りと行き詰まりつつあるので(w、
先生から新しいテーマの準備しおくように言われたのだ。で、関連文献にあたる事になる。大抵の論文はネットで手に入るが(便利な時代になったもんだ)、中にはタダでは読めないものもある。
そこで図書館の登場となる。有名どころの洋雑誌(Nature,Science,Cellとか)はかなり古いものまで保存されている。殆どのものは禁帯出なので館内で複写する必要があるが、それでも先人達の仕事を知る事ができる。
実際実験をやるにしても先行研究のあるなしで難易度が大きく変わるので、こまめな情報収集が欠かせない。疑問に思ったら「調べる」、である。(まだまだ徹底できていないが。。)
先生から新しいテーマの準備しおくように言われたのだ。で、関連文献にあたる事になる。大抵の論文はネットで手に入るが(便利な時代になったもんだ)、中にはタダでは読めないものもある。
そこで図書館の登場となる。有名どころの洋雑誌(Nature,Science,Cellとか)はかなり古いものまで保存されている。殆どのものは禁帯出なので館内で複写する必要があるが、それでも先人達の仕事を知る事ができる。
実際実験をやるにしても先行研究のあるなしで難易度が大きく変わるので、こまめな情報収集が欠かせない。疑問に思ったら「調べる」、である。(まだまだ徹底できていないが。。)
無事終了。まぁ6割は取れているでしょう。(低っ
学部二年生の時に始めて出合って以来、非常に苦手な分野であった。
理系の癖に数学・物理が苦手なのでやってて訳わからんといったらもう。。
ただ、今回改めて取り組んでみると、案外面白い分野であった。
数式をただ数式と見るのではなく、何を表しているのかを丁寧に考えると、
ただの記号がイメージに変換されていく。グラフや図を描くことが理解の助けになった。
例えば、水分子がなぜ直線系ではなく屈曲しているのか。
無機化学では混成軌道の概念で説明されるが、もっと大雑把にLCAO近似でも
屈曲する理由を説明することができる。(要は屈曲した方が分子軌道が安定化するのだ。)
4月からの講義(今度は大学院の授業になるが)も同じ先生の下で受けたいものだ。構造物理の先生は勘弁(ぉ
あとは卒研発表。パワポとの格闘の日々(ぉ
学部二年生の時に始めて出合って以来、非常に苦手な分野であった。
理系の癖に数学・物理が苦手なのでやってて訳わからんといったらもう。。
ただ、今回改めて取り組んでみると、案外面白い分野であった。
数式をただ数式と見るのではなく、何を表しているのかを丁寧に考えると、
ただの記号がイメージに変換されていく。グラフや図を描くことが理解の助けになった。
例えば、水分子がなぜ直線系ではなく屈曲しているのか。
無機化学では混成軌道の概念で説明されるが、もっと大雑把にLCAO近似でも
屈曲する理由を説明することができる。(要は屈曲した方が分子軌道が安定化するのだ。)
4月からの講義(今度は大学院の授業になるが)も同じ先生の下で受けたいものだ。構造物理の先生は勘弁(ぉ
あとは卒研発表。パワポとの格闘の日々(ぉ
colE3-Im3複合体の発現・精製
2008年11月18日 学校・勉強今日逆相HPLCの結果をSDS-PAGEで解析、f4にcolE3のバンドを確認。現在のシステムでcolE3のみを分離、精製できることが分かった。収量としては、現在のやり方ではe3,e2から合わせて1.5mgのcolE3を回収できる計算になる。
<気づいたこと>
・Im3はf9にうす~くバンドが出ただけだった。その近辺で徐々に流れたのだろう。
・HPLCに打つ前のサンプルを前処理したときに生じた沈殿は残しておくべきだった。(どの位沈殿に落ちてるかを確認するために)
・再溶解した時のpHはチェックしておく。(2xSBに溶かした時青色だったので、さほどacidicではないハズ)
・概算でHPLCによる収率は4割だったが、これは悪くない数字。(HPLCにかけると良くて5割の収率らしい。)
<今後>
・酸可溶性沈殿によるcolE3の活性評価→塩基配列既知のRNAを切断、断片をLC-MSで解析し、認識部位、切断様式を解析
進んだら進んだで面倒でぷ。(w
<気づいたこと>
・Im3はf9にうす~くバンドが出ただけだった。その近辺で徐々に流れたのだろう。
・HPLCに打つ前のサンプルを前処理したときに生じた沈殿は残しておくべきだった。(どの位沈殿に落ちてるかを確認するために)
・再溶解した時のpHはチェックしておく。(2xSBに溶かした時青色だったので、さほどacidicではないハズ)
・概算でHPLCによる収率は4割だったが、これは悪くない数字。(HPLCにかけると良くて5割の収率らしい。)
<今後>
・酸可溶性沈殿によるcolE3の活性評価→塩基配列既知のRNAを切断、断片をLC-MSで解析し、認識部位、切断様式を解析
進んだら進んだで面倒でぷ。(w
colE3 rRnase-Im3複合体の発現、精製
2008年11月12日 学校・勉強<気づいたこと>
・超遠心待ちで90minほどsonication産物をon iceで放置したが、バンドは出た。それほど分解されないらしい。(菌株がBL21(DE3)で、lonプロテアーゼ欠損だから、というのもあるか)
・C.R.の蛍光灯チェンジ、まずは先生に相談
・超遠心でも、バランス合わせは秤で良い。(TLA-45は電子天秤か?)
<やる事>
・報告準備(データ整理、説明要点の整理、結論の設定)
・BF法の準備(標準試料はBSAか?)
・関連論文漁り
・量子化学復習(式の展開も一通りさらう)
<気になること>
・PCのUSBポート不具合。(マウス以外でも試す。)
・学内でLast.fmが聞けない?
・次のテーマは何だろう?
・xbox360のアップデートはどのくらいのものか。
備忘録として記す。11/12(水)2:06
・超遠心待ちで90minほどsonication産物をon iceで放置したが、バンドは出た。それほど分解されないらしい。(菌株がBL21(DE3)で、lonプロテアーゼ欠損だから、というのもあるか)
・C.R.の蛍光灯チェンジ、まずは先生に相談
・超遠心でも、バランス合わせは秤で良い。(TLA-45は電子天秤か?)
<やる事>
・報告準備(データ整理、説明要点の整理、結論の設定)
・BF法の準備(標準試料はBSAか?)
・関連論文漁り
・量子化学復習(式の展開も一通りさらう)
<気になること>
・PCのUSBポート不具合。(マウス以外でも試す。)
・学内でLast.fmが聞けない?
・次のテーマは何だろう?
・xbox360のアップデートはどのくらいのものか。
備忘録として記す。11/12(水)2:06